霧の中で見えなかった標識
1956年、イギリス。
濃い霧に包まれたプレストン・バイパスで、一人のドライバーが標識を見逃し、危うく事故を起こしかけました。当時の道路標識は、まるで19世紀から時が止まったかのような古めかしいデザインで、高速で走る自動車時代にはまったく対応できていなかったのです。
戦後復興期のイギリスでは、自動車の普及とともに高速道路網の整備が急ピッチで進められていました。しかし、道路標識システムは旧態依然としたままでした。文字は装飾的で読みにくく、標識のデザインもバラバラ。これでは、増え続ける交通量と速度に対応できるはずがありません。

運命の出会い
そんな状況を憂慮した運輸省は、1957年、あるデザイナーに白羽の矢を立てました。その人物こそ、ジョック・キニア。彼は当時、ロンドンのチェルシー・スクール・オブ・アートで教鞭を執る傍ら、グラフィックデザイナーとして活動していました。
キニアは、この国家的プロジェクトに取り組むにあたり、一人の優秀な教え子を助手として選びました。南アフリカ出身の若き女性デザイナー、マーガレット・カルヴァートです。当時まだ20代前半だった彼女は、タイポグラフィに対する鋭い感性と、斬新なアイデアを持っていました。
二人は、まず既存の道路標識の問題点を徹底的に分析しました。そして気づいたのです。これまでの標識は「静止している人が読むもの」として設計されていたことに。しかし、時速70マイル(約112キロ)で走る車から瞬時に判読できる標識が必要な時代になっていたのです。
革新的なアプローチ
キニアとカルヴァートは、まったく新しいアプローチを採用しました。
まず、書体の開発から始めました。装飾を一切排除し、遠くからでも瞬時に判読できる「Transport」という専用書体を生み出したのです。大文字と小文字を組み合わせることで、単語の形状そのものが認識の手がかりとなるよう工夫しました。例えば「Birmingham」という地名は、その文字の上下のラインが作る独特のシルエットだけで認識できるようになったのです。
色彩システムも革新的でした。青は高速道路、緑は主要道路、白は地方道路といった具合に、色だけで道路の種類が瞬時に判別できるようにしました。
そして、最も画期的だったのがピクトグラムの導入でした。カルヴァートがデザインした「子供の横断」を示す標識には、実は彼女自身の子供時代の写真がモデルとして使われています。また、「農場の動物」を示す牛のシルエットは、彼女が休暇で訪れた農場で見た「ペイシェンス」という名前の牛がモデルでした。これらの親しみやすいピクトグラムは、言語の壁を越えて誰もが理解できるものとなりました。
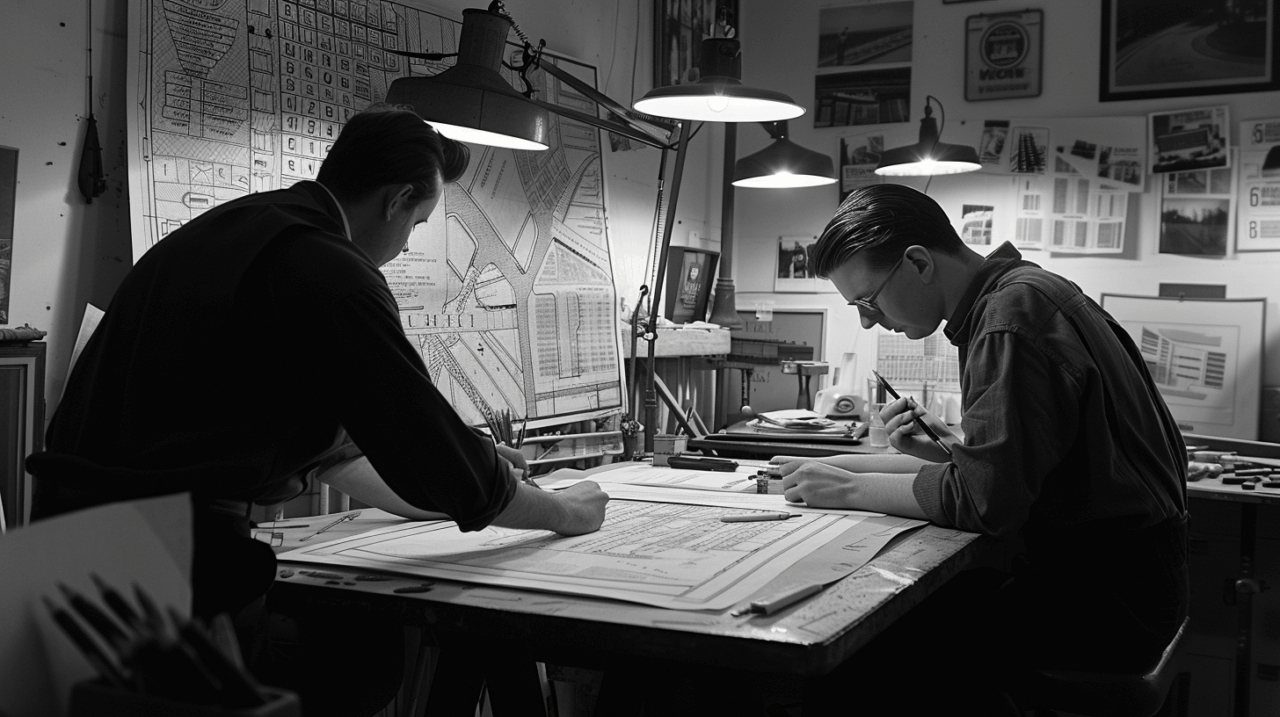
困難との戦い
しかし、この革新的なデザインへの道のりは平坦ではありませんでした。
保守的な官僚たちからは「伝統を無視している」という批判が相次ぎました。特に、小文字を使用することに対しては「権威がない」「安っぽく見える」といった反対意見が噴出しました。
また、全国の標識を一新するには莫大な予算が必要でした。財務省との激しい折衝が続き、プロジェクトは何度も頓挫の危機に瀕しました。
さらに、技術的な課題もありました。当時の製造技術では、キニアとカルヴァートが求める精密な文字間隔や、微妙な曲線を持つピクトグラムを大量生産することは困難でした。二人は製造現場に何度も足を運び、職人たちと一緒になって製造方法を改良していきました。
転機となった実証実験
1958年、プレストン・バイパスで大規模な実証実験が行われました。新しい標識システムを実際の高速道路に設置し、その効果を検証したのです。
結果は劇的でした。ドライバーたちの標識認識速度は従来の3倍に向上し、道を間違える車は激減しました。特に夜間や悪天候時の視認性の向上は目覚ましく、事故率も大幅に低下したのです。
この成功を受けて、1964年、ついに「ワーボーイズ委員会」が新しい道路標識システムの全面採用を決定しました。1965年から段階的に導入が始まり、1970年代初頭までにイギリス全土の道路標識が一新されました。
世界標準となったデザイン
キニアとカルヴァートが生み出した道路標識システムは、イギリス国内だけでなく、世界中に大きな影響を与えました。
多くの国々が、このシステムの基本原則を採用しました。香港、アイルランド、ポルトガル、アイスランド、そして多くの英連邦諸国が、このデザインシステムをベースに自国の道路標識を開発しました。
特筆すべきは、このデザインが半世紀以上経った今でも、ほとんど変更されることなく使われ続けていることです。デジタル時代になっても、カーナビゲーションシステムや自動運転技術の中で、キニアとカルヴァートが確立した視覚言語は生き続けています。
デザインの普遍性
現在、イギリスの道路には約450万個の道路標識が設置されています。毎日、何百万人ものドライバーが、意識することなくこれらの標識から情報を得て、安全に目的地へと向かっています。
Transport書体は、道路標識だけでなく、イギリスの公共交通機関や政府機関の案内表示にも広く採用されています。ロンドンの地下鉄駅や空港、病院など、公共空間のあらゆる場所で、この書体が人々を導いています。
2015年、マーガレット・カルヴァートは大英帝国勲章(OBE)を受章しました。授賞理由は「道路標識とタイポグラフィへの貢献」でした。80歳を超えた今も、彼女は「良いデザインとは、人々がその存在を意識しないほど自然に機能するもの」という信念を持ち続けています。

Q&A
- なぜTransport書体は大文字と小文字を混在させているのですか?
- 単語の形状(ワードシェイプ)を活かすためです。すべて大文字だと長方形のブロックになってしまいますが、大文字と小文字を組み合わせることで、各単語が独特のシルエットを持ち、高速走行中でも瞬時に認識できるようになります。
- キニアとカルヴァートのデザインで最も革新的だった点は何ですか?
- 「動いている視点」からの視認性を最優先したことです。従来の標識は静止した状態で読むことを前提としていましたが、彼らは時速100キロ以上で移動する車内から瞬時に判読できることを設計の出発点としました。
- なぜイギリスの道路標識は他のヨーロッパ諸国と異なるデザインなのですか?
- イギリスは1968年のウィーン道路標識条約に署名していないためです。キニアとカルヴァートのシステムが既に完成度が高く、効果的に機能していたため、国際標準に合わせる必要性を感じなかったのです。
- 現在もTransport書体は更新されているのですか?
- はい、デジタル時代に対応するため、定期的に改良が加えられています。2015年には「Transport New」という改訂版がリリースされ、スクリーン表示での視認性が向上しました。
参考文献
- Jock Kinneir Library – Kingston University
- https://www.kingston.ac.uk/jock-kinneir/
- Design Museum – Margaret Calvert
- https://designmuseum.org/designers/margaret-calvert
- UK Government – Traffic signs manual
- https://www.gov.uk/government/publications/traffic-signs-manual
- The Typography of UK Road Signs
- https://www.roads.org.uk/articles/typography-uk-road-signs
基本データ
- プロジェクト名称
- British Road Sign System Redesign
- 主任デザイナー
- ジョック・キニア(Jock Kinneir, 1917-1994)
- 共同デザイナー
- マーガレット・カルヴァート(Margaret Calvert, 1936-)
- 委託機関
- 英国運輸省(Ministry of Transport)
- 開発期間
- 1957-1964年
- 全面導入
- 1965年開始
- 採用書体
- Transport(Heavy, Medium)
- 主要採用国
- イギリス、アイルランド、香港、ポルトガル、アイスランド等





コメントを残す