18世紀のロンドン、ある男の野望
1786年のロンドン。産業革命の熱気に包まれたこの街で、一人のスコットランド人技術者が、密かに革命的な本の出版準備を進めていました。彼の名はウィリアム・プレイフェア。その本は『商業政治地図帳』(The Commercial and Political Atlas)という、一見すると退屈な経済書に見えるものでした。
しかし、ページをめくった人々は驚愕しました。そこには、これまで誰も見たことのない「絵」が描かれていたのです。数字の羅列ではなく、美しい曲線と色彩で描かれた、イングランドの貿易データ。これこそが、人類史上初めての統計グラフ、つまり折れ線グラフと棒グラフの誕生の瞬間でした。
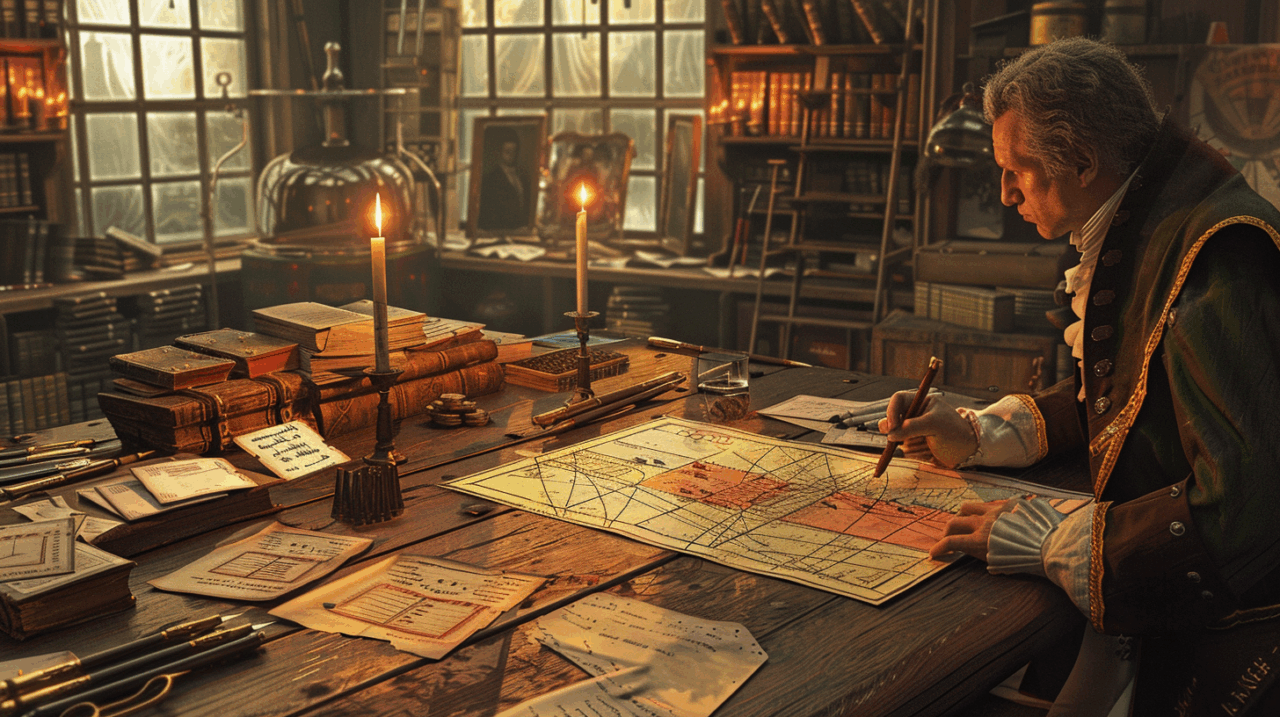
数字の海に溺れた時代
18世紀後半のイギリスは、まさに情報爆発の時代でした。植民地貿易の拡大、産業革命による生産量の増大、複雑化する国家財政。政府や商人たちは、膨大な数字の山と格闘していました。当時の経済データは、延々と続く数字の表として記録され、その理解には何時間、時には何日もかかりました。
プレイフェアは後にこう書いています。「不完全に獲得された情報は、不完全にしか記憶されない。印刷された表を注意深く調査した人も、読み終えた時には、読んだ内容についてぼんやりとした部分的な理解しか持っていない。それは砂に刻まれた図形のように、すぐに完全に消え去ってしまう」
この問題意識こそが、彼を革新へと駆り立てたのでした。
波乱万丈の青春時代
ウィリアム・プレイフェアは1759年、スコットランドのダンディー近郊で生まれました。父は牧師でしたが、ウィリアムが13歳の時に他界。長兄のジョン(後にエディンバラ大学の数学教授となる)が家族の面倒を見ることになりました。
若きウィリアムは、脱穀機の発明者アンドリュー・ミークルの下で見習いとして働き始めます。その後、蒸気機関の改良で有名なジェームズ・ワットの工房で製図工として働きました。ここで彼は、技術図面を描く技術と、複雑な機械の動きを視覚的に表現する能力を磨いたのです。
しかし、プレイフェアの人生は決して順風満帆ではありませんでした。銀細工師、技術者、投資ブローカー、経済学者、統計家、パンフレット作家、翻訳家、土地投機家、銀行家、そして時には詐欺師とさえ呼ばれることもありました。フランス革命ではバスティーユ襲撃に参加したという噂もあり、後にはイギリス政府の秘密諜報員として活動していたとも言われています。
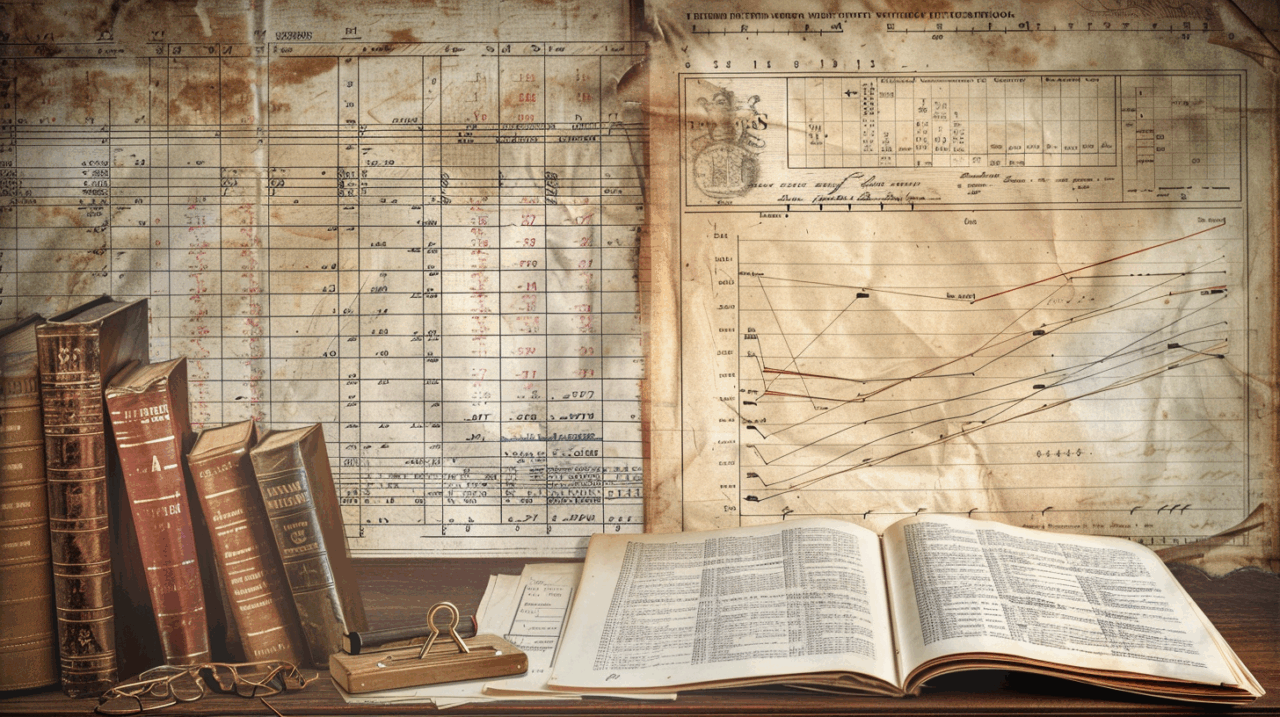
革命的なアイデアの誕生
1785年、プレイフェアは兄ジョンとの会話からヒントを得て、時間の経過に伴うデータの変化を線で表現するというアイデアを思いつきました。それまでにも、ジョセフ・プリーストリーが1765年に個人の寿命を棒で表現するタイムラインチャートを作成していましたが、経済データを線グラフで表現するという発想は全く新しいものでした。
最初の『商業政治地図帳』には43種類の折れ線グラフが含まれていました。しかし、スコットランドの貿易データについては時系列データが不足していたため、苦肉の策として1781年の1年分のデータを17の貿易相手国別に棒の長さで表現しました。これが偶然にも、世界初の棒グラフの誕生となったのです。
理解されなかった天才
プレイフェアは自信満々でした。「グラフを読むことに慣れれば、1日かけて表を調べる内容を5分で理解できる」と豪語していました。しかし、当時の人々の反応は冷ややかでした。数字は数字として見るべきであり、絵にするなど邪道だという批判も少なくありませんでした。
それでもプレイフェアは諦めませんでした。1801年には『統計要覧』(Statistical Breviary)を出版し、ここで初めて円グラフを発表しました。オスマン帝国内のヨーロッパ人、アフリカ人、アジア人の人口比率を表現するために考案されたこの手法は、部分と全体の関係を一目で理解できる画期的なものでした。
孤独な晩年と遅すぎた評価
プレイフェアの人生は、まさに浮き沈みの連続でした。銀行を設立しては破産し、詐欺の疑いで投獄されることもありました。彼の革新的なグラフ技法も、生前はほとんど評価されることはありませんでした。1823年、彼は貧困のうちに64歳でこの世を去りました。統計の英雄としてではなく、ただの統計の一つとして。
しかし、歴史は時に正義を為します。19世紀後半、イギリスの経済学者ウィリアム・スタンレー・ジェヴォンズがプレイフェアの手法を再発見し、自身の経済地図帳に応用しました。これをきっかけに、統計グラフは急速に普及し始めたのです。
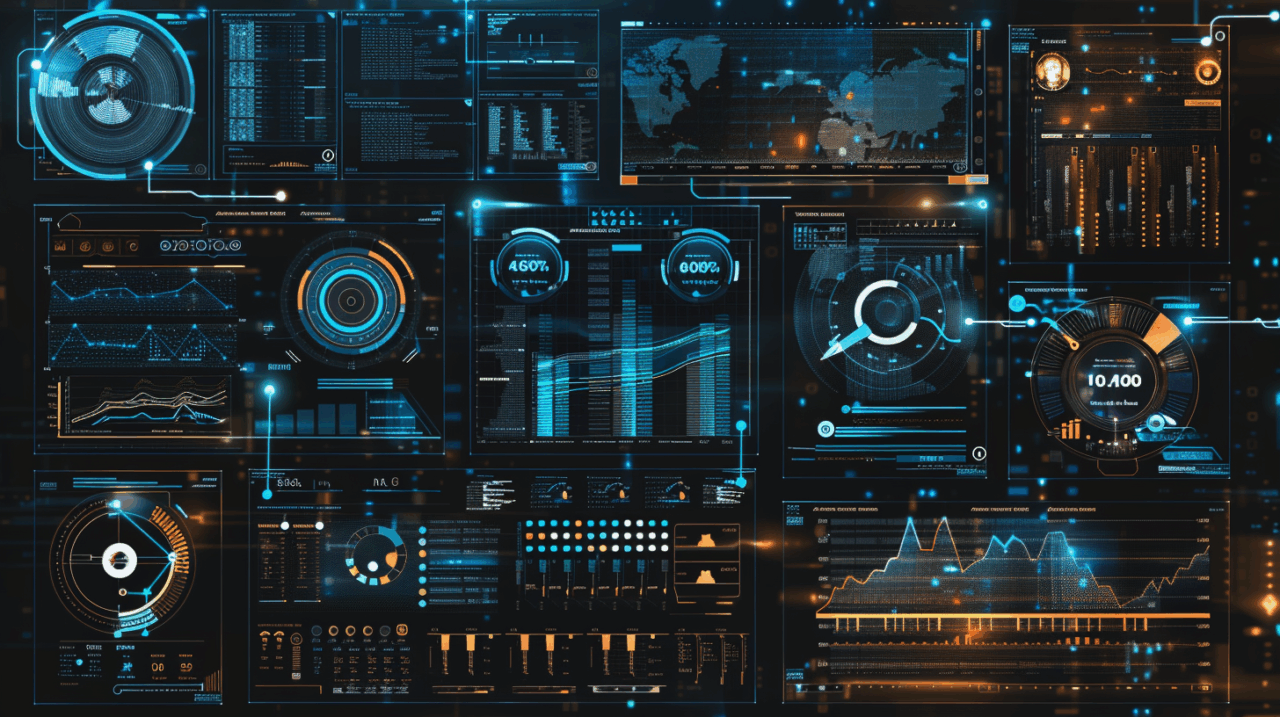
その後の世界
プレイフェアが発明した統計グラフは、現代社会のあらゆる場面で活用されています。ビジネスの世界では、売上データの分析から経営戦略の立案まで、グラフなしには考えられません。科学研究では実験結果の可視化に、教育現場では複雑な概念の説明に、メディアでは情報の伝達に欠かせないツールとなっています。
特に21世紀に入ってからは、ビッグデータ時代の到来により、データビジュアライゼーションの重要性は飛躍的に高まりました。現在では、インタラクティブなダッシュボード、3Dグラフィックス、リアルタイムデータの可視化など、プレイフェアが想像もしなかった形でデータが表現されています。
しかし、基本原理は変わりません。複雑な情報を視覚的に分かりやすく伝えるという、プレイフェアが200年以上前に確立した原則は、今も私たちのデータ理解の基盤となっているのです。
Q&A
- プレイフェアはなぜグラフを発明できたのですか?
- プレイフェアは製図工としての経験があり、複雑な機械の動きを視覚的に表現する技術を持っていました。また、兄が数学教授だったことから数学的な素養もあり、これらの要素が組み合わさってグラフの発明につながりました。さらに、18世紀後半の情報爆発という時代背景も、視覚的なデータ表現の必要性を生み出していました。
- なぜプレイフェアのグラフは当初受け入れられなかったのですか?
- 当時の人々にとって、数字を絵で表現することは全く新しい概念でした。伝統的に数字は表形式で扱うものという固定観念があり、グラフという革新的な手法を理解し受け入れるには時間が必要でした。また、プレイフェア自身の評判(詐欺師として知られていた面もある)も、彼の発明の普及を妨げた要因の一つでした。
- 円グラフはどのような経緯で生まれたのですか?
- 1801年、プレイフェアはオスマン帝国内の人口構成を表現する方法を探していました。全体に対する部分の割合を視覚的に示すために、円を分割するというアイデアを思いつきました。これが世界初の円グラフとなり、後にアメリカ合衆国の土地分布を示すためにも使用されました。
- プレイフェアの発明は現代にどのような影響を与えていますか?
- プレイフェアの発明は、現代のデータサイエンスとビジネスインテリジェンスの基礎となっています。ExcelやTableauなどのツールで日常的に使われる折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフは、すべてプレイフェアの発明が原点です。ビッグデータ時代において、データの可視化はますます重要になっており、彼の功績は計り知れません。
参考文献
- William Playfair – Wikipedia
- https://en.wikipedia.org/wiki/William_Playfair
- Jonathan Sachs, “1786/1801: William Playfair, Statistical Graphics, and the Meaning of an Event” | BRANCH
- https://branchcollective.org/?ps_articles=jonathan-sachs-17861801-william-playfair-statistical-graphics-and-the-meaning-of-an-event
- William Playfair Founds Statistical Graphics, and Invents the Line Chart and Bar Chart : History of Information
- https://www.historyofinformation.com/detail.php?entryid=2929
- Masters series: William Playfair, the father of statistical graphics | Flourish
- https://flourish.studio/blog/masters-william-playfair-father-of-statistical-graphics/
- William Playfair and the Beginnings of Infographics | SciHi Blog
- http://scihi.org/william-playfair-and-the-beginnings-of-infographics/
基本データ
- 名称
- 『商業政治地図帳』(The Commercial and Political Atlas)
- 著者
- ウィリアム・プレイフェア(William Playfair)
- 初版発行
- 1786年(ロンドン)
- 発明
- 折れ線グラフ、棒グラフ(1786年)、円グラフ(1801年)
- 生没年
- 1759年9月22日 – 1823年2月11日
- 出身地
- スコットランド、ダンディー近郊





コメントを残す