今、当たり前に見ている路線図の原点
東京の地下鉄に乗るとき、私たちは色分けされた直線と45度の角度で構成された路線図を何の疑問も持たずに眺めています。ニューヨーク、パリ、ベルリン、世界中のどの都市を訪れても、同じような幾何学的なデザインの路線図に出会うでしょう。しかし、この「当たり前」は、わずか90年前には存在しませんでした。
1933年1月、ロンドンの地下鉄利用者たちは、ポケットに収まる小さな路線図を手にして驚きました。それまでの地図とはまったく違う、まるで電気回路図のような、あるいはモンドリアンの絵画のようなデザイン。これこそが、一人の失業中の製図工が生み出した、世界の交通マップを永遠に変えることになる革命的なデザインだったのです。

混沌とした地下世界への挑戦
1920年代のロンドン地下鉄は、急速な拡張の真っ只中にありました。1908年に初めて全路線を表示した地図が登場しましたが、それは実際の地理的な位置関係を忠実に再現したもの。中心部の駅は密集して判読が困難で、郊外の駅は遠く離れて描かれていました。複雑に入り組んだ路線は、まるでスパゲッティのように絡み合い、利用者にとって理解することは困難を極めていました。
そんな中、ハリー・ベック(Henry Charles Beck)という29歳の若者が、ロンドン地下鉄の信号部門で製図工として働いていました。1931年、世界恐慌の影響で一時的に職を失った彼は、自宅で時間を持て余していました。その時、彼の頭に一つのアイデアが浮かびます。「地下鉄の利用者は、駅の実際の位置を知りたいのではない。どの駅でどの路線に乗り換えればいいかを知りたいだけなのだ」
拒絶から受容へ、革新的アイデアの苦難
ベックは、地理的な正確さを完全に捨て去りました。曲がりくねった路線を垂直線、水平線、45度の対角線だけで表現し、駅間の距離を均等にし、中心部を拡大して郊外を圧縮。唯一残した地理的要素は、様式化されたテムズ川だけでした。
1931年、彼がこのデザインを地下鉄の広報部門に持ち込んだとき、反応は冷たいものでした。「あまりにも急進的すぎる」「地理的な距離感がまったくわからない」。提案は即座に却下されました。しかし、ベックは諦めませんでした。翌1932年、彼は改良版を再提出します。今度は、試験的に500部だけ印刷することが許可されました。
その反響は予想を超えるものでした。利用者からの反応は圧倒的に好意的で、1933年1月、ついに75万部の本格的な印刷が決定されます。わずか1か月で増刷が必要になるほどの人気でした。フランク・ピック(Frank Pick)という、ロンドン交通局のデザインに深い理解を持つ経営者も、「これまでのどの地図よりも優れている」と認めざるを得ませんでした。
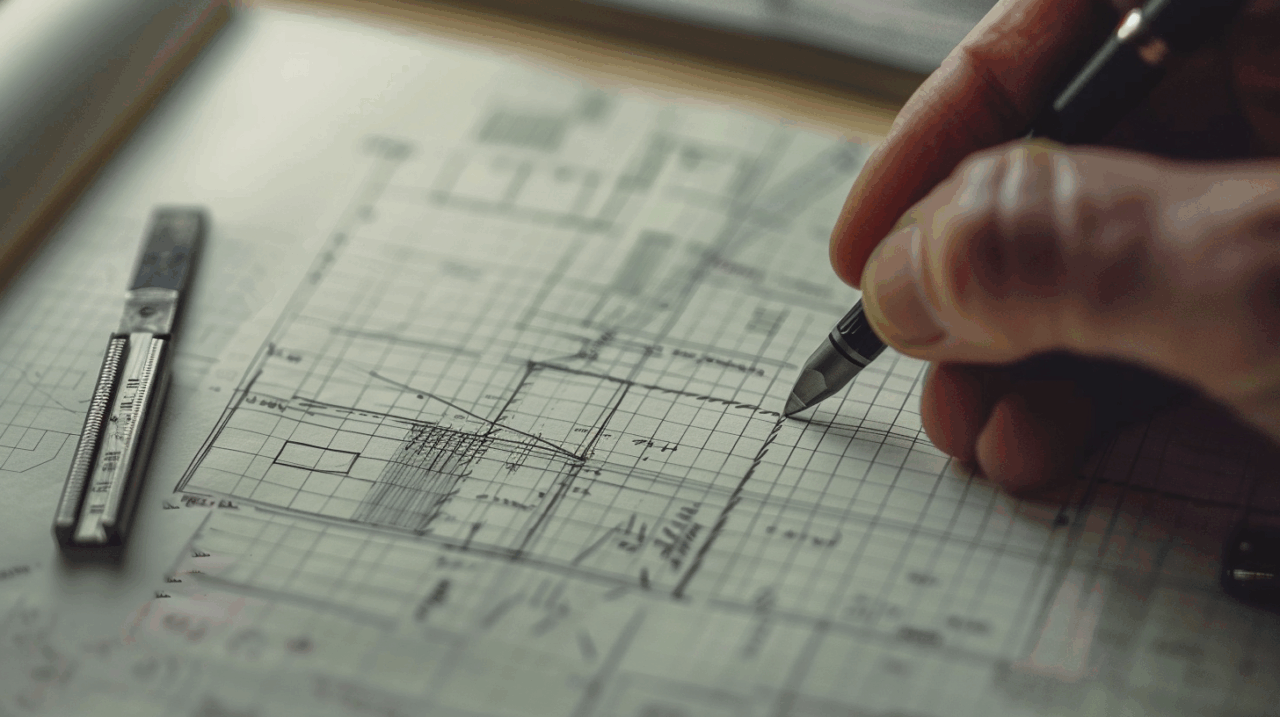
世界標準となったデザイン言語
ベックの革新は、単なる地図の簡略化ではありませんでした。彼は、複雑な情報を整理し、視覚的に理解しやすくする新しい「言語」を創造したのです。色分けされた路線、円で囲まれた乗換駅、規則的な角度と間隔。これらの要素は、瞬く間に世界中に広がっていきました。
1939年、シドニーがベックのデザインをほぼそのまま採用(一部では「盗用」とも言われました)。1950年代にはニューヨークが、1960年代には東京が、1970年代にはモスクワが、そして1980年代にはマドリードとバルセロナが、ベックの原則を取り入れた路線図を導入しました。現在では、世界中のほぼすべての都市交通システムが、ベックの影響を受けたデザインを使用しています。
デジタル時代でも生き続ける普遍性
90年が経った今でも、ベックの基本原則は変わっていません。スマートフォンのアプリで見る路線図も、駅構内の巨大なパネルも、すべてベックが確立した視覚言語を使用しています。東京メトロの路線図を見れば、駅番号システムやカラーコーディングなど、ベックの思想が息づいていることがわかります。
興味深いことに、ベックはこの革命的なデザインに対して、わずか5ギニー(現在の価値で約800ポンド)しか受け取りませんでした。彼は1959年まで路線図の主任デザイナーを務めましたが、組織との関係は必ずしも良好ではありませんでした。1974年に亡くなったとき、彼の功績はほとんど認識されていませんでしたが、現在では「このダイアグラムは1931年にハリー・ベックが考案したオリジナルデザインの進化版です」という一文が、すべてのロンドン地下鉄路線図に記載されています。

その後の世界
ハリー・ベックの路線図デザインは、単に交通機関の案内図を変えただけではありません。情報デザインという分野全体に革命をもたらしました。複雑な情報を簡潔に、美しく、理解しやすく表現するという彼のアプローチは、現代のインフォグラフィックス、ユーザーインターフェース設計、データビジュアライゼーションの基礎となっています。
また、ベックの路線図は都市のアイデンティティにも影響を与えました。路線図は単なる移動の道具から、都市の象徴、アート作品、さらには観光グッズのモチーフへと進化しました。世界中の都市が競うように独自の路線図デザインを開発し、それが都市のブランディングの一部となっています。デジタル時代においても、リアルタイム情報や乗換案内アプリなど、新しい技術と融合しながら、ベックの基本原則は生き続けています。
Q&A
- Q. なぜハリー・ベックの路線図は革命的だったのですか?
- A. ベックは地理的な正確さを捨て、利用者が本当に必要とする情報(駅の順序と乗換情報)だけに焦点を当てました。垂直線、水平線、45度の対角線のみを使用し、駅間の距離を均等にすることで、複雑な地下鉄網を理解しやすい幾何学的なダイアグラムに変換しました。この革新的なアプローチは、それまでの地図の常識を覆すものでした。
- Q. ベックのデザインはなぜ最初は拒絶されたのですか?
- A. 1931年当時、地図は地理的に正確であることが当然とされていました。ベックの提案はあまりにも急進的で、実際の距離や位置関係がわからないことが問題視されました。しかし、試験的な配布で利用者から絶大な支持を得たことで、その実用性が証明されました。
- Q. 現在の東京の路線図もベックの影響を受けていますか?
- A. はい、大きな影響を受けています。色分けされた路線、規則的な角度、駅番号システムなど、東京メトロや都営地下鉄の路線図にもベックの設計原則が採用されています。特に2020年の東京オリンピックに向けて、より分かりやすい標準化された路線図の開発が進められました。
- Q. ベックは他にどのような仕事をしていましたか?
- A. ベックは路線図以外にも、パリメトロの路線図デザインや、イギリス国鉄の郊外路線図なども手がけました。また、ロンドン交通局の社内誌のカバーデザインや、職員の肖像画なども描いており、多才な芸術家でもありました。
参考文献
- Harry Beck’s Tube map – Transport for London
- https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/culture-and-heritage/art-and-design/harry-becks-tube-map
- Transforming the Tube map: Harry Beck’s iconic design
- https://www.ltmuseum.co.uk/collections/stories/design/transforming-tube-map-harry-becks-iconic-design
- Harry Beck – Wikipedia
- https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Beck
- The Genius of Harry Beck’s 1933 London Tube Map–and How It Revolutionized Subway Map Design Everywhere
- https://www.openculture.com/2018/04/the-genius-of-harry-becks-1933-london-tube-map.html
基本データ
- 名称
- ロンドン地下鉄路線図(London Underground Map)
- 設計者
- ヘンリー・チャールズ・ベック(Henry Charles Beck)
- 初版発行
- 1933年1月
- 発行部数(初版)
- 750,000部
- 報酬
- 5ギニー(約5.25ポンド)
- デザイン期間
- 1931年(初案)〜1933年(採用)
- 主任デザイナー在任期間
- 1933年〜1959年





コメントを残す